

トラックドライバーって事故が多いとクビになるの?
何をしたらクビになっちゃうの?
こんな悩みにお答えします。
運転の仕事をする以上、交通事故は避けては通れない現実です。
誰だってわざわざ迷惑をかけたくて交通事故を起こしているわけではありません。
とくにトラックドライバーは「車両も大きく」「運転時間も長い」ことから交通事故のリスクは増えてしまいます。
当然ですが、事故の多いドライバーは会社の信頼も低くなり、場合によってはクビとなるケースもあります。
残念ですがボクの周りの仲間にも「事故でクビ」となったドライバーが何人かいました。
この記事では、過去の事例や実体験をもとに
「どんなドライバーが事故を起こしやすいのか」
「どんなポイントを攻略すれば事故を回避できるのか」
こんな点に絞ってお伝えしていきます。
「トラックドライバーとして気をつけるポイント」を知ることで、ドライバー人生に大きな差が出てきます。
【トラック運転手がクビ】になるケース
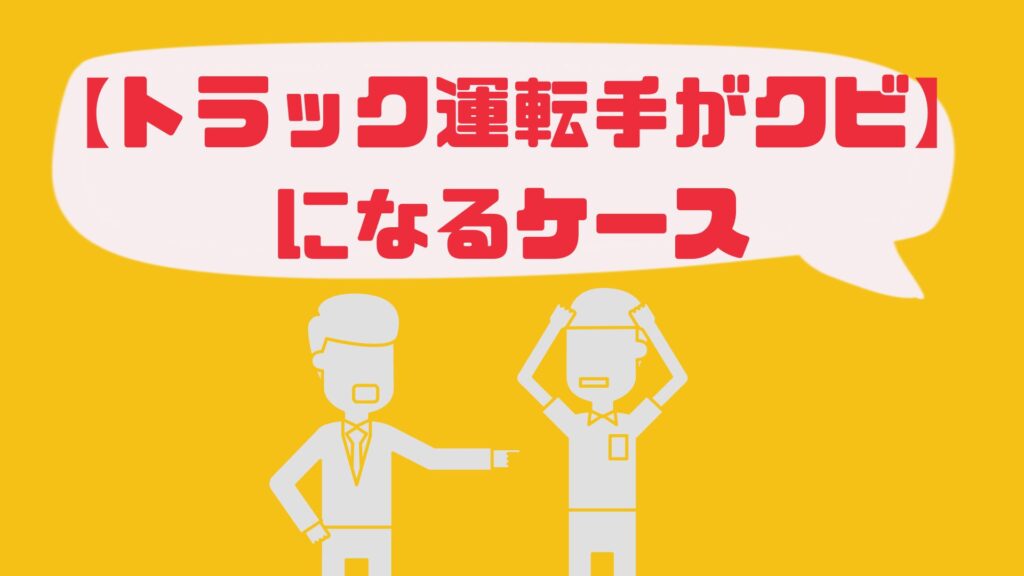
トラックドライバーがクビになるケースは、どのような時なのでしょうか?
主な原因はさまざまですが、1つの理由として「トラックの運転を任せられない」と会社側が判断したときです。
クビと言っても懲戒解雇とは違い、話し合いや面談の末「自主退社」を促されるケースが想定されます。
「トラックの運転を任せられない」ドライバーの特徴
- 急ブレーキ・急ハンドル・急発進
- 居眠り運転・よそ見運転
- 運転マナーが悪い
上記のようなドライバーは要注意です。
なぜ安全運転は必要なのか
運送業は荷主・顧客から荷物を預かり、目的地へ配送することが目的です。
預かった荷物を正確かつ安全に輸送できて、初めて運賃が発生します。
信用ある仕事から継続的な業務を任せてもらいます。
その結果、事業が安定するのです。
信用を蓄積していくのは「配送ドライバー」の仕事です。
荷物を大切に扱うことはもちろん、運転技術や運転マナーも重要となります。
当然、会社はドライバーに対し安全運転の指導・教育を行なっていくのです。
会社の考え方
最悪なケース、重大事故1つで信頼が崩れてしまう可能性があるのです。
企業同士の信頼がなくなれば当然、仕事は回ってこなくなります。
その結果、同僚の仕事も失う可能性もあるのです。
会社はドライバーを教育・指導し「仕事を任せられる人材」を育成します。
そのため「トラックの運転を任せられない」と判断した場合は、
話し合いや面談の末「自主退社」を促す場合があります。
社会的立場
また、トラックは車両が大きく重量もあるので、交通事故が重大化しやすい傾向があります。
運送会社は国土交通省の監視により、ドライバーに適切な指導・監督の義務が行われています。
つまり運転技術や運転マナーをドライバーに育成することが会社の務めとなり、
ドライバーは安全運転スキル・マナーを向上していく必要があるのです。
安全運転を継続することで、会社・顧客・荷主から信頼を得ることができます。
クビになるドライバーの特徴
また、クビになるドライバーの特徴として
- アルコールチェックに引っかかる
- 交通事故が多いドライバー
この2つに関しては、会社は重要事項ととらえ「社員をクビ」にするポイントとなってきます。
なぜなら、 放置しておくと重大事故を引き起こし大惨事となる可能性が生じるからです。
重大事故に関しては、会社・ドライバーにとってデメリットしかありません。
会社としては経営すらおぼつかない状態となってしまいます。
アルコールチェックに引っかかるドライバー
会社は「あなたのアルコール習慣をチェック」し「ドライバー適正」を判断します。
適切なアルコール摂取の管理ができないドライバーはクビ(懲戒解雇)の原因となってしまいます。
具体的な過去の事例としては
アルコールチェックの不正操作
「アルコールチェックをしない」「他者にチェックさせる」などの不正操作が発覚し、懲戒解雇が適用された。
勤務外での飲酒(酒気帯び)運転による交通事故を起こしてしまい、信用を失いクビとなった。
度重なるアルコールチェック違反、会社の指導にも応じず「改善の余地がない」と判断され懲戒解雇となる。
こんな事例がありました。
「お酒の管理ができないドライバー」は会社からの信用を失い、「トラックドライバーには向いていない」と判断される傾向があります。
アルコールチェックとは?
アルコールチェックとは何?と思ったあなたに「アルコールチェック」について説明します。
トラックドライバーは業務を始める前に運行前点検・アルコールチェックを行います。
飲酒運転による事故漠滅のため、平成23年5月1日より「運行前アルコールチェック」の義務が導入されました。
出社し「トラックに乗る前」に必ず運行管理者の対面(状況によりオンライン対応も可)によるアルコールチェックを受けます。
ちなみにボクの会社では下の機械を使用しております。
メーカー・機種はさまざまですが、PCで管理できるタイプが主流です。

「運行前」「運行後」の1日2回、アルコールチェッカーを使用し体内のアルコール量を計測します。
会社の規定にもよりますが、アルコール残量ゼロが基本です。
上記のアルコールチェックを通過して、トラックの運転・操作ができます。
お酒が好きなドライバーは注意
お酒が好きな人は特に「出社前の運行前」に注意が必要です。
アルコールチェックを通過しなければその日の運行ができません。
ちなみに、体内からアルコールが抜けるまでの時間は、
・ビール中瓶1本(アルコール度数5%・500mL)
・グラスワイン2杯(アルコール度数12%・200mL)
上記に量で「男性は約4時間」「女性は約5時間」となっています。
もちろん個人差はあり、その日の体調などでアルコール分解時間は変化します。
一概には言えませんが、参考値として認識しておいて下さい。
飲酒運転は操作ミス・判断ミスを招き、とても危険です。
重大事故・死亡事故などに直結するので、会社は厳しく管理しています。
ハンドルを握るからには「プロ意識」は必要です。
アルコールの習慣は自己管理と認識しましょう。

交通事故が多いドライバー
交通事故が多いドライバーは、スキル不足が考慮され「問題社員」として取り扱われてしまします。
理由として、そんなドライバーを放置しておくと重大事故を引き起こす原因となるからです。
重大事故には「人身・死亡事故」いわゆる人の命に関わる事故も含まれます。
亡くなった命は取り戻せません。
最悪のケース、人身事故を起こした社員はクビ(解雇)となります。
道路交通法では、人身事故は刑事事件となります。
損害賠償義務が生じ、社会的責任が課せられます。
とくに旅客・運送業は厳しく処分される傾向があります。
人身事故を起こしたドライバーの処分
人身事故を起こしたドライバーは「免許」にも影響が生じます。
免停・免取り(行政処分)→トラックの運転ができない
最低でも、免停となります。
免取り処分も覚悟が必要です。
つまり、「トラックを運転できない」=「仕事がない」状況となります。
免停中のドライバーは、「新人教育」「業務のノウハウを教える」などの横乗り指導くらいしか仕事がなくなってしまいます。
また、運送会社によっては「倉庫業のお手伝い」くらいはあるかもしれません。
はっきり言って、免停・免取りのドライバーは会社のお荷物です。
このような状態になると、同僚・上司との関係も悪くなってきてます。
戦力外を感じてしまうと働きがいもなくなるし、会社に行くのも嫌になるでしょう。

会社とドライバーの関係性

いくらドライバーに問題があれど、会社はクビ(懲戒免職)を宣告することは難しいです。
民法では「労働者が有利な法律」が執行され、使用者が一方的にクビにできないシステムとなっているからです。
雇用側は「従業員の生活を保障する義務」が生じます。
そのため、社員をカンタンにクビにできないのです。
しかし、問題社員を野放しにしておくと他の従業員や業務に支障が出てきます。
会社としては悩みの原因です。
会社からみるトラックドライバー「問題社員」は以下の3つです。
問題社員
- 事故が多いドライバー
- 運転マナーが悪いドライバー
- 集中力がないドライバー
このような「問題社員」を会社はどのように扱っているのでしょうか?
深掘りして説明します。
会社側から見る【問題社員】の特徴
安全運転ができないドライバーは【問題社員】とレッテルを貼られ、危険視されるでしょう。
やはり、常に安全運転ができること、これがトラックドライバーとして最低限の条件なんです。
まずは、安全運転で毎日過ごすことが何よりの信頼となります。
余談ですが、常に安全運転で運転マナーに定評のあるドライバーであれば「多少のミスや遅れは許される」なんてこともあるんです。
ようするに「人間性」がとても重要であり、普段から蓄積していくスキルと言えるでしょう。
こちらに関しては、下記事にて詳しく解説しています。気になる人は参考にしてください。
-

-
未経験からトラックドライバーに転職|「向き不向き」を17項目で説明
> 転職 > 未経験からトラックドライバーに転職|「向き不向き」を17項目で説明 トラックドライバーの転職には「ドライバーズワーク【トラック】」がオススメです。 専任キャリアアドバイザーが ...
続きを見る
懲戒処分となるケース
事故が原因でクビになるケースは実在します。
たとえば中小企業・ワンマン社長のいる会社では、一方的にクビにするケースもあります。
理由として、顧客・元請会社に「ドライバーの処分を迫られた」「今後の仕事が貰えなくなる」など
つまり、仕事の存続に関わる選択が迫られた状態です。
仕事は信用第一です。特に中小企業の場合は、定期業務が1つなくなると経営が傾いてしまいます。
かといってすぐに新規の業務を獲得することも難しいのが現状です。
「問題を起こした社員を出入り禁止」とすることで、現状の仕事を維持してもらい折り合いをつける場合もあります。
厳しいですが現実に起きることなんです。
ボクの事例ですが、
過去にアップル製品を配送誤納をしてしまい、その責任として「営業所の出入り禁止」を命じられました。
残念ながら会社・企業は株主優先で仕事をするのが現実なんです。
「大切な株主」の信頼を失うこと、すなわち仕事・契約がなくなることに直結してしまいます。

解雇・クビは難しい問題
会社は【社員をクビ・解雇】に対し消極的であり、行動しない傾向があります。
理由の1つに、法律上の問題があります。
日本の法律は、使用者(会社)側が強くなりすぎないように、労働者優位な設計がされているのです。
こうすることで労働者の雇用が守られます。
しかし会社としては、問題の多い社員を抱えることで「社風や士気が下がる原因」となり懸念されます。
そして何より、安易にクビを宣告した場合、状況にもよりますが裁判に発展する恐れがあるんです。
裁判ともなれば「お金」「時間」がかかるばかりではなく、会社の信用やイメージにも問題が生じてしまいます。
よって、会社としては「社員をクビや解雇すること」に消極的な思考となるのです。
クビになる前に「退職」してしまう

あなたと相性の悪い会社にずっといても、良いことなんてないかもしれません。
新しい環境で「1からやり直す」ほうが、あなたにとってメリットがある場合もありますよね。
でも、会社の上司に退職届けを出すのが面倒、退職の理由など聞かれるのがわずらわしい、なんて思っていませんか?
そんなあなたには「退職代行サービス」を利用することをオススメしています。
退職代行サービスとは、労働者の権利を駆使して「最速で退社をするサービス」です。
具体的には、民法627条にある「労働者の雇用解除の申し入れ」の条件をもとに、弁護士や法的責任のある人がこの法律を上手に活用して、あなたの代わりに退職の手続きを執行してくれるサービスとなっています。
627条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申し入れをすることができる。この場合において、雇用は解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する。
民法627条より
退職代行サービスを利用するには、2~3万円ほどお金がかかります。
正直、少し高額です。
しかし、休業手当や失業給付金などを活用すれば、十分に払える金額です。
上司とのやり取りや「辞めるまでの気まずい期間」もなく退職できるサービスは、ストレスフリーで時間短縮にもなります。
退職はプロにお任せする時代です。ご興味のある人は、下記事を参考にしてみてください。
-

-
失敗しない退職代行の使い方|「メリット」「デメリット」をぶっちゃけ公開します
「退職代行サービスで失敗したくない」 「サクッと退職して、次の会社で頑張りたい」 悩む人 でも、退職代行サービスって ボクでも使えるか心配 退職代行サービスを使ってみたいけど、上手く使える自信がない。 ...
続きを見る

